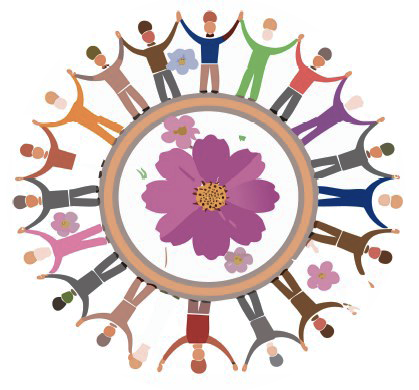12月18日
このテーマの最後、日本の障害者施策の経緯「1990年代後半から現代」までを医学的・社会モデルなどを踏まえていきます。
● 地域生活支援の充実と新たな法的取り組み: 交通バリアフリー法、身体障害者補助犬法など、移動や社会参加を促進する法整備が進展。らい予防法、エイズ予防法の廃止・改正により、感染症患者の人権が尊重されるようになる。障害者自立支援法施行により、従来の措置制度から契約制度へ移行。医療観察法、発達障害者支援法が制定。特別支援教育が推進。高次脳機能障害への支援も始まる。
●問題点:
・障害者に対する介護の家族依存が深刻化、家族への負担が大きい。
・障害者雇用について、ILO条約勧告からの指摘。
・障害者自立支援法の利用者負担や制度設計を巡り、反対運動や紛争。
・医療観察法、発達障害者支援法に課題が残る。
・特別支援教育は分離教育の形態が維持。
・医学モデル・社会モデル: 障害者自身のエンパワメントや社会参加を促進する動きが進む一方、家族依存や雇用問題など、社会モデルの実現には依然課題が残る。
●考察できる事柄:
• 障害者自立支援法への移行は、利用者本位のサービス提供を目指したものの、利用者負担の増加やサービス利用の複雑化などの問題を生んだ可能性。
•家族介護の負担は、社会資源の不足や地域包括ケアシステムの構築の遅れなどが背景にあると考えられる。
•障害者雇用問題は、企業側の理解不足や雇用機会の不足、合理的配慮の提供不足などが課題と考えられる。
•特別支援教育における分離教育の継続は、インクルーシブ教育の推進という国際的な潮流に逆行している可能性。
•医療観察法は、精神障害者の社会復帰支援と犯罪予防という二つの目的のバランスが課題となる可能性。
•発達障害者支援法は、早期発見・早期支援体制の整備や、ライフステージに応じた支援の提供などが課題と考えられる。
●全体を通しての考察
•ノーマライゼーションの理念は浸透したものの、社会モデルへの転換は道半ばであり、法制度や社会環境、国民の意識改革が継続的な課題である。
•障害者福祉政策は、時代の要請や国際的な潮流、障害当事者団体の運動など、様々な要因に影響を受けて変遷しており、今後の政策立案においては、これらの要素を十分に考慮する必要がある。
•医学モデルから社会モデルへの移行は、障害を個人の問題から社会の問題として捉え直す大きな転換であり、更なる社会環境の整備と国民の意識改革が不可欠である。特に、障害者の自己決定権の尊重、インクルージョン社会の実現、合理的配慮の提供などが重要な課題となる。
このように分類し考察することで、日本の障害者福祉の歴史的変遷における課題の所在と、今後の方向性についてより深く理解することができます。
さていかがでしたでしょうか?戦前、戦後、現代までふまえて医学的、社会モデルをお伝えしてきましたが日本の福祉制度は欧米より他の国より遅れているとは、言われますが他の国の方から見ると「充実している、日本は福祉社会」といわれる方も見えます。
もう少し深堀してみましょう
1.日本の福祉制度の現状と課題
・法律・制度の整備と複雑性: 法律は整備されているものの、複雑さが課題
・地域参加の促進: 地域での共生が進んでいる一方で、課題も
・差別と偏見: 封建社会の名残か、障害者に対する差別や偏見が根強い
・健常者優位思想: 健常者と障害者の二分法がもたらす問題
2.神奈川殺傷事件、障害施設での暴行事件から考える
・事件の背景: 障害者に対する蔑視が根底にある
・加害者の心理: 健常者と障害者の違いを強調することで、自らの優位性を確立しようとする心理
・健常者とは何か: 健常者と障害者の境界線は曖昧であり、単純な二分法は意味をなさない
3.多様性を認め合う社会へ
・個人の尊厳: 人は皆、生まれながらにして平等な権利を持つ
・差別と偏見をなくすために: 自らを見つめ直し、多様性を認め合う
・共生社会の実現に向けて: 社会全体で障害者に対する理解を深め、共に生きる社会を築く
まとめ: 福祉制度は、社会全体で取り組むべき課題である
今後の展望: よりインクルーシブな社会の実現に向けて、私たち一人ひとりができること
*読者への問いかけ: あなたは、多様性のある社会をどのように実現したいですか?
12月17日
前回の続き日本の障害者施策の経緯「1980年代から1990年代前半」までを医学的・社会モデルなどを踏まえていきます。
•国際的な潮流とノーマライゼーション: 国際障害者年(1981年)や障害者に関する世界行動計画(1982年)の影響を受け、ノーマライゼーションの理念が普及。施設入所中心から地域福祉への転換が始まり、在宅福祉サービスが法定化。障害者基本法制定により三障害(身体障害、知的障害、精神障害)の統一が図られる。精神保健法制定により精神障害者の処遇改善が図れました。
•問題点:
・在日外国人障害者を含む無年金者の問題。
・精神障害者の処遇改善が不十分。
・児童の権利条約の批准が遅れ、統合教育は発展せず。
・医学モデル・社会モデル: ノーマライゼーションの理念に基づき、社会モデル的な考え方が示唆され始める。
考察できる事柄:
•ノーマライゼーションの理念が導入されたものの、具体的な制度設計や社会環境整備が追いついていなかった可能性。
•在宅福祉サービスの法定化は大きな前進だが、サービス内容や提供体制の充実度は地域差があった可能性。
•統合教育の遅れは、教育現場の理解不足や受け入れ体制の不備などが原因として考えられる。
•精神障害者の処遇改善は、長期入院の解消や地域生活への移行支援などが課題だったと考えられる。
•無年金者問題は、制度の狭間にある人々への対応の遅れを示しており、制度設計の包括性が課題だったと考えらます。
まだまだこの当時は問題が色々生じているのがわかります。次回は1990年代後半から現在までどのように変わってきて現在の福祉のことに触れてみたいと思います。それではまた次回に。
12月13日
日本の障害者問題の経緯 「1960年時代、1970年時代」をお話していきましょう。
1960年代
●経済成長とその拡大: 高度経済成長を背景に、国民年金法に基づく福祉年金の支給開始、身体障害者雇用促進法制定など、障害者への結果保障や就労支援が進展しました。
●問題点:精神薄弱者福祉法制定により、障害種類ごとの侵害が展開され、知的障害者等の入所施設が増加しました。これは、ノーマライゼーションや脱施設化といった世界的な動向とは逆行するものでした障害児教育は分離別学のままで、統合教育への動きは見られませんでした精神障害者については、精神衛生法改正や医療金融公庫法施行により、科病院への勧告が促進されました。
●医学モデル・社会モデル:経済的自立を目的とした就労支援は社会モデル的な要素と言う方、施設主張中心の明示や分離教育は医学モデル的な考え方が強く反映されたものでした。
1970年代
●表明の体系化と新たな課題への対応:精神障害者対策基本法制定により、障害者侵害の基本が示されましたが、精神障害者は認められたままでしたスモン薬害問題を契機に、難病対策要綱が示され、調査研究、医療施設整備、医療費負担軽減といった対策が始まりました身体障害者雇用促進法が改正され、法定賃金率制度の義務化と納付金制度が導入されました養護学校が義務教育となり、障害児の就学全員体制が準備されましたが、分離教育の形態は維持されました。
●問題点:心身障害者対策基本法は、予防発生や施設被害といった保護に力点を考えている4、障害者の社会参加や権利といった視点が抜けていました。
●医学モデル・社会モデル:医学モデルに基づいて継続が行われる、雇用促進や新興機会の拡大など、社会モデル的な要素も見られます。
共に高度経済成長期にはいります。その時代の問題点などをまとめてみます。
高度経済成長期
*問題点:
・高度経済成長に伴い、障害者に対する社会の関心が薄れた。
・施設への収容が中心となり、地域生活は困難であった。
・障害者の自立生活や社会参加は遅れていた。
*モデル:
・医学モデル: 医療機関を中心とした支援が続いた。
・社会モデル: ノーマライゼーションの理念が日本に紹介され、障害者の地域生活や社会参加が求められるようになった。
*障害者問題における過程:
・障害者基本法が制定され、障害者の権利が保障されるようになった。
・障害者自立支援法が制定され、障害者の地域生活への移行が促進された。
問題点にあります地域生活や社会参加が求めらや今の地域参加には程遠いものでした。
また障害者自立支援法においてもこの後それぞれ問題点があり今の総合支援法に変わってきました。
次回は1980年時代以降現在までをお伝えできればと思います。
12月12日

前回日本の障害者問題の経緯 時代「戦後」からの続きをお話していきましょう。
2戦後直後
・飛躍の転換点:GHQの指示と日本憲法における福祉の確信により、生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法などの福祉三法が制定されたこれにより、行政による福祉サービス提供の基礎が築かれました学校教育法制定により、障害児にも特殊教育という形で教育の機会が与えられました。
●問題点:予算の保留から医学モデルに基づく障害等級による制限が行われ、福祉法の対象も限定された訓練主義や保護主義的な要素が重視され、「愛される障害者像」といった問題も存在していた。
・戦争による障害者が増え、福祉サービスの需要が高まった。
・障害者に対する社会的な差別や偏見は根強く残っていた。
・福祉サービスは十分に整備されておらず、障害者の生活は困難であった。
●医学モデル・社会モデル:医学モデルに基づく障害等級による制限が行われた方、教育機会の提供など社会モデル的な要素も一部見られます。
・医学モデル: 戦後の復興期には、障害者の医療的なケアが優先された。
・社会モデル: 社会復帰や社会参加の重要性が認識され始め、徐々に社会モデルへの転換が進み始めた。
●障害者問題における過程:
・障害者福祉法の制定など、障害者に対する社会的な支援が始まった。
・障害児養護施設の整備が進められた。
・障害者の雇用促進策が講じられた。
*基本的な原型のモデルがこの当時に行われました。社会的な差別や偏見やまだまだ福祉サービスは十分に整備されていませんでしたのでの生活は困難のようでした。このころから社会的な支援、障害児養護施設、雇用促進などが行われ現代にも受け継がれています。
次回は1960時代、1970年時代をあげてみます。
12月10日 ブログ
ちょっと重たい題材ですが「日本の障害者施策の経緯」というものを挙げてみました。長くなるのでそれぞれの年代ごとに振り返ってみようと思います。長くなりますので年代ごとで分けて投稿していきたいと思います
日本の障害者問題の経緯:時代別問題点と医学モデル・社会モデルの対比
Ⅰ.戦前・戦中
1.問題点: 障害者は国家政策において、人権対策の対象、または精神障害者の場合は安全・取締りの対象とみなされていました1個別対立は存在したもの、「家族依存」が先決で、家族以外による保護は民間依存でした国内補償対象はほぼ傷痍軍人に限定されておりました。
わかりやすくしてみましょう
・障害者は社会から隔離され、医療施設や療養所への収容が一般的であった。
・教育の機会は限られ、社会参加は困難であった。
・優生思想の影響を受け、障害者の存在は否定的に捉えられる傾向にあった。
2.医学モデル・社会モデル: 障害者に対する国内の貢献が限定的であったため、医学モデルと社会モデルの対比は明確ではありません。
・医学モデル: 障害を個人の身体的な欠陥と捉え、医療による治療や改善を重視。
・社会モデル: 社会構造や環境が障害を生み出すという考え方はまだ定着していなかった。
3.障害者問題における過程:
・障害者は社会の負担とされ、医療や福祉の対象として扱われた。
・優生保護法の制定など、障害者の存在を否定する政策が採られた。
これらの優生保護法に於いてはいまでに論争が続いておりますが、健常者優位との古来からつづいてきたものがそのまま根付いてきたものです。これ以降欧米諸国からの考えなどが取り入れられて施策も変わってきましたが現代においても古来からの日本人における蔑視は続いてままが嘆かわしいです。
次回は戦後になります。
12月9日 職員ブログ
12月に国際障がい者デーなど制定された障害福祉に関する記念日・条例・設立などをどんなものがあるでしょう。
12月は、国際障害者デーをはじめ、障害者の権利や福祉向上に向けた様々な取り組みがスタートした重要な月です。日付ごとに、記念日、条例、設立などを分類してご紹介します。
12月3日
国際障害者デー: 1992年に国連総会で制定。障害者の権利と福祉の向上を目的とし、世界中でイベントが開催されます。
12月9日
障害者の日: 日本では、1981年の国際障害者年に際して、障害者に対する理解を深めるために制定されました。
その他
条例制定: 各自治体において、障害者の権利保障や生活環境の整備に関する条例が12月に制定されるケースもあります。
施設の設立: 障害者福祉施設の開設や、障害者支援団体が発足するケースも12月に見られます。
3日~9日までは障害者週間というものが定められました。さて?障害者週間とはなんなのでしょう。簡単に要約してみましたのでよろしかったらお読みください。
「障害者週間」は、毎年12月3日から12月9日までの1週間です。この1週間は、国民の間に障害者福祉への関心と静かに、障害者が社会のあらゆる分野に積極的に参加する活発な活動を高めることを目的としています。
「障害者週間」設定の背景には、以下の出来事があります。
●1975年12月9日:「障害者の権利宣言」が国連総会で承認。
●1982年12月3日:「障害者に関する世界行動計画」が国連総会で承認。
これらの出来事を記念して、日本では12月9日を「障害者の日」、12月3日を「国際障害者デー」と定めました。そして、1992年には、国際障害者デーから障害者の日までの1週間を「障害者週間」とすることを決定しました。
2004年6月の障害者基本法改正により、「障害者の日」は「障害者週間」に拡大され、法律に基づくものとなりました。
「障害者週間」では、国、地方公共団体、関係団体など様々な意識啓発活動を行います。内閣府はこれらの関連行事を取りまとめて発表しています。
12月5日 ブログ
12月4日



12月3日更新